悪性新生物(がん)による障害年金申請
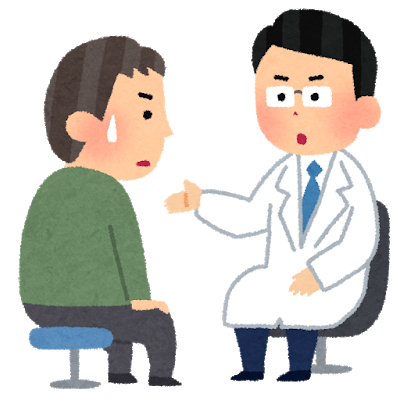
弊所にも、年間を通じ悪性新生物による障害年金申請のご相談が多く寄せられています。
国立がん研究センターの統計(2014年データに基づく)によれば、日本において生涯にがんに罹患する確率は、男性62%(2人に1人)、女性47%(2人に1人)とされています。
これだけ多くの方が罹患する傷病でありながら、それにより、障害年金の支給対象となる場合があることについて、あまり知られていないのではないかと感じています。
どのような方であれば悪性新生物の症状により障害年金受給の可能性があるのでしょうか?
障害年金を受給するためには、大前提として年齢の要件や年金納付要件があります。
- 原則として被保険者期間中(国民年金・厚生年金)に初診日があること。 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のあるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
以上の2つの条件を満たしている上で、障害の程度が障害認定基準に定める程度の状態であることが必要です。どのくらいの状態であれば何級に該当するのか?という点については、次の項でご説明します。
障害年金の請求に際し、必ず提出しなければならないものの一つ、「診断書」を準備する際のポイントは?
ポイントは2つあります。
- 診断書(様式120号の7)には病状・治療の経過や全身状態をできるだけ詳しく具体的に記載してもらいましょう
- 症状に合わせた診断書を別途準備することも検討しましょう
まず、1つ目のポイントについてご説明します。
1. 診断書(様式120号の7)には病状・治療の経過や全身状態をできるだけ詳しく具体的に記載してもらいましょう
悪性新生物による障害年金の基準は、「国民年金・厚生年金障害認定基準」により定められています。悪性新生物の場合はまず「血液・造血器・その他の障害用の診断書(様式120号の7)」という診断書様式を準備することとなりますが、この診断書の中の「⑫一般状態区分表」において、ア~オのどの区分で記載されるかが、どの障害等級に認定されるかの一つの目安となっています。
| 区分 | 一般状態 | 障害等級の目安 |
|---|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | 非該当 |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など | 3級 |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | 2級又は3級 |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | 2級 |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの | 1級 |
悪性新生物は全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる症状は様々で、それによる障害も様々です。よって上記の一般状態区分だけで一律に判断されるのではなく、
- 組織所見とその悪性度
- 一般検査及び特殊検査の結果
- 血液検査、画像検査の結果
- 転移の有無
- 病状の経過や治療効果(治療頻度、腫瘍マーカーの結果やステージ等)
- 身体所見
等も含め、総合的に認定されることになっています。
ここで、総合的に認定してもらうためには、診断書に上記の事柄に加え、日常生活能力の支障を詳細に書いてもらうことが大事です。そのためには、診断書を作成してもらう医師にしっかりご自身の症状や日常生活の現状を伝えることが必要です。短い診察時間の中で日々の状態を伝えることが困難な場合は、文書にして渡す等の工夫も必要かもしれません。医師に伝わっていなければ、診断書に反映してもらうことは難しくなります。治療前と後での体重の変化や、日常生活上の介助状況などが診断書に記載されているとよりよいでしょう。
次に、2つ目のポイントについてです。
2. 症状に合わせた診断書を別途準備することも検討しましょう
悪性新生物によって現れている症状が全身衰弱だけでなく、体の機能障害にも表れている場合は、先ほど説明した診断書(様式120号の7)だけでなく、症状にに合った別の種類の診断書を提出することを考えてみましょう。
例えば以下のような場合です。
- 乳がん→手術による後遺症で手足が不自由になっている→肢体の疾患用の診断書
- 咽頭がん、食道がん→治療の後遺症で食事摂取に困難がある→そしゃく・嚥下障害用の診断書
障害年金の認定は、医療機関の診察のように請求者(患者様)と対面することはなく、提出された診断書や申立書などの書面のみで審査されます。どんなに症状が重くても、日常生活に困難が生じていても、その症状や日常生活上の様子が診断書に記載されていなければ、「その症状はなかったもの」として審査が進んでしまいます。
最初に準備した診断書(様式120号の7)だけでは現しきれない症状がある場合は、それぞれの症状に合わせた別の診断書の提出が有効となります。
まとめ
悪性新生物を発症され、日常生活に困難を抱えていらっしゃる方には、障害年金の受給の可能性があることをお伝えしました。
せっかく申請に向け書類を準備しても、ポイントから外れてしまっていては受給の可能性を広げることが出来ません。
障害年金の請求には、揃えなければならない書類が多岐にわたり、申請から受給まで半年近くかかることも珍しくありません。なるべく早くお手続きの準備に取り掛かることが重要です。